
今こそ「基礎」を固めよう
2022/1/10
後期選抜まで2ヶ月を切りました。
刻一刻と試験の日が近づいてきています。
難しい問題が続々と
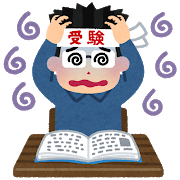
1月、2月は学校のテストや模試が続きます。
「入試近くのテスト」ということで、難易度もこれまで受けてきた中で最も難しいレベルの内容となってきます。
難しい問題が出題されれば、解けない可能性も高くなります。
その結果、思うように点数が伸びず、焦るようになります。
そこで、多くの受験生が「難しい問題」に手を出すようになっていきます。
ですが、多くの場合「効果的な対策」にならないことが多いです。
難しい問題が解けない理由
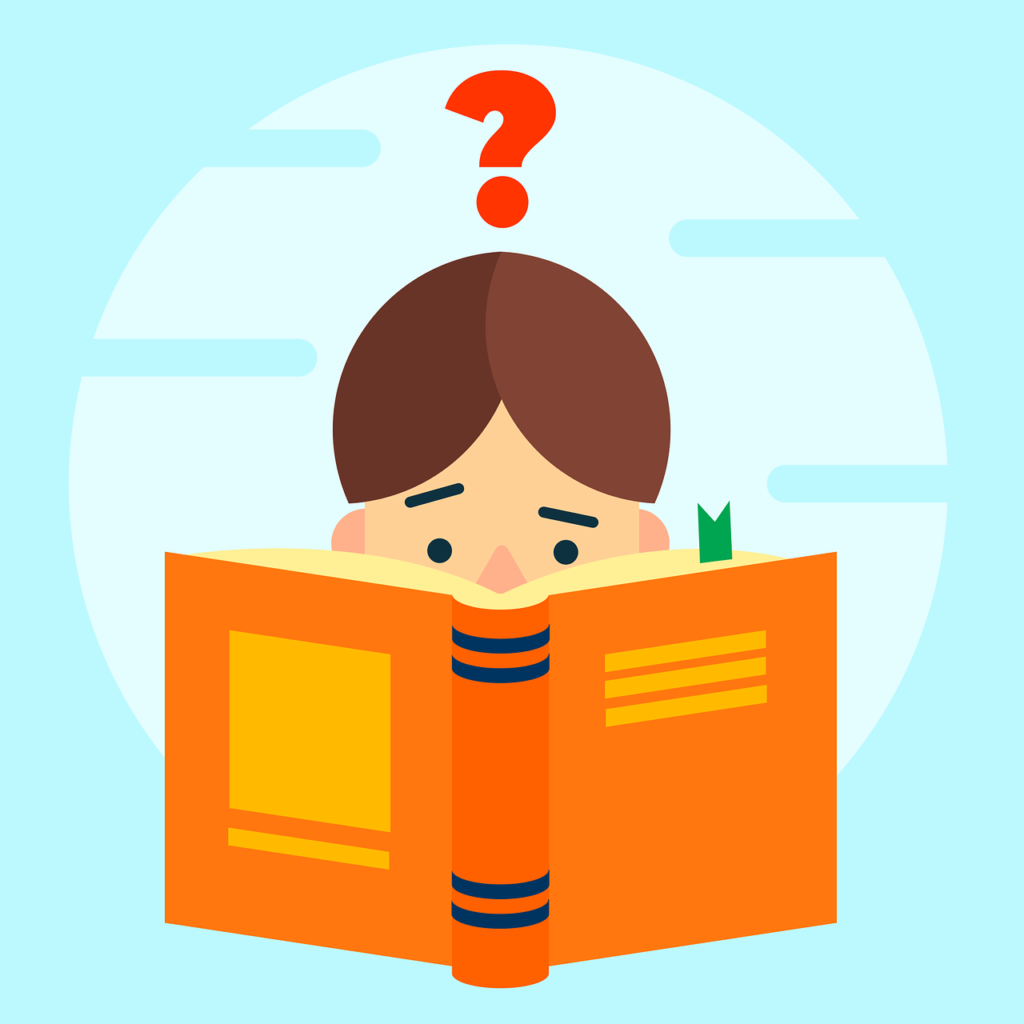
難しい問題が解けない子のほとんどの理由は「基礎知識不足」です。
難しい問題というのは、一般的に「基礎知識が組み合わさってできている」ことが多いです。
1つ1つ分解すれば基本的な内容が、積み重なった形で出題されています。
なので、基礎がしっかりしている生徒であれば、その組み合わせを1つ1つていねいに解き進めることができ、最終的に答えまでたどり着くことができます。
一方、基礎がまだ未定着の生徒は、「どのような基礎知識を使うのか」が見抜けないため、そこで立ち止まってしまいます。
その結果、最後までたどり着かないで終わる、というケースが多いです。
まず「基礎」を固める
基礎がしっかりしていないのに、どれだけ難しい問題を解いても力はつきません。
「穴の空いたバケツで水をすくう」ような感じで、ポロポロと知識がこぼれ落ちてしまうような感覚です。
難しい問題を闇雲に解くのではなく、解いたあとで、「基礎的な部分で未定着の部分はないか」をまず確認する。
そして、もしまだあいまいな部分があれば、その部分に立ち返って基礎部分をもう一度練習する。
こうした地道な作業をすることで、初めて難しい問題は解けるようになってきます。
上位校を目指す生徒ほど気をつける
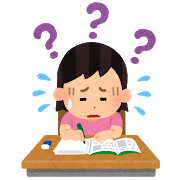
「難しい問題にハマって点数が伸び悩む」のは、上位校を目指す生徒に多いです。
以前いた生徒で、このようなことがありました。
上位の高校を目指していた生徒。数学の点数がなかなか伸びないことに悩んだその生徒は、年末から1月にかけて、応用問題ばかりを解くようになりました。
その生徒の質問の様子から「まだ基礎がわかっていない」と感じたので、
「あまり難しい問題ばかりに目を向けず、もう一度基礎部分を確認するように」
というアドバイスをしました。
ですが、あせりからか、こちらのアドバイスは届かず、その後も応用問題ばかりを解き続けていました。
そして2月のテスト。ボロボロの結果となりました。
「このままでは本当にマズイ」
そう感じたので、残りの1ヶ月、徹底的に「基礎」の復習をさせました。
最終的に、入試にはなんとか間に合いましたが、もしあのまま「難しい問題ばかり」を解き続けていたら…、と思うとゾッとします。
迷ったときほど「基礎」
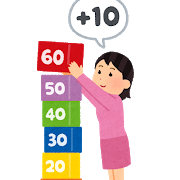
これからのテストは1回1回の重みがこれまでと違ってきます。
テスト結果に一喜一憂するのが普通です。
ただ、その時にあせって、ただ難しい問題を繰り返さないことが大事です。
「自分がまだ身についていない基礎知識はないか?」
ということに真正面から向き合い、1つ1つていねいにできるようにしていく。
迷った時ほど「基礎」練習です。これを意識するようにしてほしいと思います。
☆YouTubeチャンネルもやっています
https://www.youtube.com/channel/UCcorE8DZR8FqA_EX2tlHo-A/featured?view_as=subscriber
ぜひご覧ください。